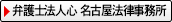1 仮執行宣言付の敗訴判決について上告提起・上告受理申立てをした場合にも、控訴提起を行った場合と同じく、強制執行の停止の申し立てをすることができる旨、民事訴訟法403条1項2号が定めています。
ただし、その要件は、①原判決の破棄の原因となるべき事情があること、及び、②判決により償うことができない損害を生ずるおそれがあることについての疎明が必要であり、控訴の場合の要件である、①原判決の取消し・変更の原因となるべき事情がないとはいえないこと、または、②執行により著しい損害を生ずるおそれがあること、と比べると、かなり厳しい要件であることが明らかです。
申立書には、上告理由・上告受理申立て理由に記載するべき内容を記載することが要求されることになりそうです。
2 強制執行停止の申立てを行い、裁判所が認容する場合には、担保提供命令を発し、法務局に供託したことを証する書面(供託書)を裁判所に提出することにより強制執行停止決定が出されます。
刻一刻を争う状況で、以上の書面のやりとりを裁判所と法務局で行う必要があり、また、供託する金額が大きい場合には、電子納付や振込等の選択なども非常に神経を使います。
また、担保提供命令の決定は、書面でなされることが通常と考えられますが(主文は、例えば、「申立人は、本決定の告知を受けた日から7日以内に、担保として金●万円を供託しなければならない。」というようなものです。)、口頭で告知することでも可能とされており(電話で告知されます。)、供託時に不安になる要素となります。
控訴提起時の場合の主文は、例えば、「前記仮執行宣言付判決に基づく強制執行は、本案控訴事件の判決があるまで、これを停止する。」というようなものです。
3 それでは、上告提起・上告受理申立て時に供託が必要となる金額は、控訴提起時に供託した金額の差額を供託すればよいのでしょうか?
この点については、差額を供託すればよいとは考えられておらず、上告・上告受理申立て時の担保提供命令の金額を供託しなければ、供託が受け付けられることはなく、強制執行停止命令も出されません。
さらに、上告・上告受理申立て時の担保提供命令の金額を供託した場合にも、控訴の際に供託した供託金を取り戻すことができないと判断した大阪地裁昭和36年2月20日決定があり、民事訴訟を取り扱う弁護士としては注意が必要です。
会社法136条は、譲渡制限株式を第三者に譲渡しようとする場合、当該株主は、会社に対し、譲り受けようとする者の氏名等の事項を明らかにしたうえで、その譲渡を承認するかどうかの決定をするように請求することができることを定めています。
会社は承認するか否かを決定して通知する必要がありますが、株主の請求の日から2週間以内に通知をしないと、原則として承認する決定をしたものとみなされます(会社法145条1号)。
同時に、株主が、譲渡の承認をしないときに会社または会社が指定する者が買い取るよう請求することもでき、会社が承認しないときには、会社が買い取る決定若しくはか買い取る者を指定することが必要となります(会社法140条)。
さらに、会社または会社が指定した者が1株当たりの純資産額に対象となる株式数の数を乗じた額を本店所在地の供託所に供託して通知することが必要となり(会社法141条1項、会社法142条1項、会社規則25条)、通知をしない場合には第三者への譲渡が承認されたものとみなされてしまいます(会社法145条2号)。
特に交通事故の刑事責任が問題になる場合、同時並行的に、免許の取消処分の手続きが行われることが通常であり、弁護士の立場からアドバイスを行うべき場合も多くあります。
例えば、聴聞の手続きを経て免許取消処分が行われ、その後刑事手続きとしては不起訴処分となった場合にはどのように考えるべきでしょうか。
故意が問題となるような構成要件について、検察官は、取調べの結果やそれまでの捜査も踏まえて、不起訴処分にした場合、その構成要件該当性について嫌疑が十分ではないことを理由に不起訴にしたものと考える場合が多いと考えられます。
道路交通法上の行政処分と刑事処分は、目的や手続を異にするものであり、相互に独立した処分であることは当然のことではありますが、免許取消処分を行うに当たり検察庁とは異なる独自の資料が認定に用いられたとは考えられず、基本的には刑事記録のみにより処分をされていることや、不起訴処分と近接した日に行われていること等からは、行政処分と刑事処分とは全く同様の事情に基づき判断がされているといえる場合が多いでしょう。
それにもかかわらず、刑事処分において不起訴とされた事実を認定して、全く逆の事実認定に基づき免許取消処分という行政処分を行うことについて、行政処分と刑事処分の目的の違いという抽象的な理由だけでは、一般市民の強い違和感を払拭することはできないでしょう。
審査請求の審理は、愛知県では、愛知県警察本部交通部運転免許課が原処分の正当性を主張する書面を提出し、愛知県公安委員会(窓口は、愛知県警察本部警務部監察官室)が判断することになっています。
証拠として収集されているドラレコの映像を確認することができ、刑事事件捜査とは証拠のアクセスの観点から異なる規律が採用されています。
無免許で運転してしまった場合にも、道路交通法違反等の罰金前科がある場合には、公判請求されるケースは珍しくありません。
無免許運転をした行為自体を争うことは難しいケースがほとんどですので、情状を中心に主張や証拠収集を含めた立証活動が行われます。
具体的には、発覚当日の運転経路をスマホのGPS機能を操作して裏付けとして使ったり、車検証等の走行距離と当該自動車に表示される走行距離の差を被告人の運転距離として特定するなどが行われます。
当然、発覚した直接の経緯等も審理の対象となります。
一旦無免許運転をしてしまうと、警察等に見つからない限りは日常的に犯してしまう傾向にあることは否定できませんが、検察官や裁判所からは、常習性や道路交通法規範に対する軽視や鈍麻を指摘されてしまうのも特徴といえるでしょう。
被告人にとって重要な活動としては、いかに繰り返さないかについて具体的な対策を考えることです。
同居する家族の協力や、場合によっては、勤務先の協力が得られるかもポイントになりえます。
なお、二度と車には乗らないことを誓約する考え方もある一方で、免許取得することの必要性を十分に理解することで、欠格期間経過後には、再取得する方針をとり、再取得することの障害を取り除く方向で具体的に検討するべき場合もあります。
特に、無免許運転をしてしまい、公判請求を受けて裁判対応が必要となってしまった場合には、弁護士にご相談ください。
NISAは、日本版ISAの略で、イギリスのISAを参考に平成26年1月1日から施行されており、少額投資非課税制度とも呼ばれています。令和5年までのNISA(「旧NISA」といいます。)は、つみたてNISA、一般NISA、未成年を対象とするジュニアNISAがありました。令和6年から始まった新NISAでは、つみたて投資枠、成長投資枠に統合されましたが、全体としては大幅に拡充されました。
iDeCoは、individual-type Defined Contribution pension planの略で、一般に、個人型確定拠出年金と呼ばれています。公的年金(国民年金・厚生年金)とは別の私的年金の位置づけの制度です。
通常、株式や投資信託などの金融商品から得た利益に対しては20.315%の課税(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)がされますが、NISA、iDeCoとも、運用時に得た利益には課税されません。
iDeCoでは、積立時において、積立額・掛金が所得控除され、所得税・住民税を軽減することができますが、原則60歳以降にしか受け取れないという制約があります。受取り時には、「退職所得控除」、「公的年金等控除」の適用を受け、一定金額までは非課税となります。余剰資金を強制的に積立できるという意味でプラスにとらえることも可能です。
NISAでは、受取時にも課税がされません。
しかしながら、あくまで投資によって利益が発生した場合に課税されないという制度ですので、元本割れのリスクや、損益通算ができないというのは、忘れてはいけないデメリットといえるでしょう。
新NISAには、18歳以上という年齢制限以外には、特に加入資格の制限はありません。
iDeCoは、次の方などを除き、国民年金の被保険者である65歳未満の方が加入できます。
① 国民年金の保険料納付免除(一部免除含む)、納付猶予を受けている方(障害基礎年金の受給者を除く)
② 農業者年金に加入している方
③ 企業型確定拠出年金の加入者の方でマッチング拠出(企業型確定拠出年金において、事業主が負担している掛金に上乗せして、加入者自身も掛金を拠出できる制度)を利用している場合
④ 企業型確定拠出年金の加入者の方で事業主掛金が年単位拠出の場合
⑤ iDeCoの老齢給付金を受給された方、公的老齢年金を繰り上げ受給された方
なお、所属する弁護士法人では、企業型確定拠出年金制度を採用しています。
iDeCoでは、職業ごとに上限が設定されており、例えば自営業やいわゆるフリーランスの方などの「第1号被保険者」の場合は月額6万8000円、会社員などの「第2号被保険者」は、企業年金への加入状況などにより、月額1万2000円から2万3000円とされています。
新NISAでは、非課税の保有期間が恒久化されたほか、年間の投資上限枠が最大360万円、生涯に投資できる枠も1800万円と大幅に増え、十分な税優遇制度という評価もなされています。
また、iDeCoは、加入している従業員の加入者掛金に、事業主掛金を上乗せして拠出するiDeCo+(イデコプラス)という制度もあります。
1 iDeCoとは、国民年金・厚生年金の公的年金とは別に、給付を受けるための私的年金制度です。
iDeCoは、individual-type Defined Contribution pension planの略で、イデコとよばれています。
公的年金と異なり、加入は強制ではなく、加入の申込や、掛金の拠出、掛金をどのような金融商品に運用するかをご自身の選択で行い、税制上の優遇を受けたうえで、掛金とその運用益をもとに給付を受け取ることができます。
iDeCoに加入するためには、iDeCoを取り扱っている金融機関等で加入手続きを行う必要がありますが、大手のネット証券会社は基本的に取り扱っているようです。
2 iDeCoは、以下の方を除き、国民年金の被保険者である65歳未満のすべての方が加入できることになっています。
・国民年金の保険料納付免除(一部免除含む)、納付猶予を受けている方(障害基礎年金の受給者を除く)
・農業者年金に加入している方
・企業型確定拠出年金の加入者の方でマッチング拠出を利用している場合(「マッチング拠出」とは、企業型確定拠出年金で事業主の掛金に上乗せして、加入者自身も掛金を拠出する制度です。)、事業主掛金が年単位拠出の場合
・iDeCoの老齢給付金を受給された方、公的老齢年金を繰り上げ受給された方 など
3 したがって、企業型確定拠出年金加入者であっても、マッチング拠出を利用していない場合や、事業主掛け金が年単位でない場合には、掛け金の上限の範囲であれば、加入できることになります。
1 はじめに
株式や投資信託などの金融商品を売却して得た利益や、受け取った配当金等に対しては、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)がかかります。
しかし、NISA(少額投資非課税制度)の適用を受けることにより、上記の株式や投資信託などの金融商品から得られる利益や配当金等は非課税の扱いを受けることができます。
令和6年からは、このNISAが大幅に拡充されます(「新NISA」と呼ばれています)。
もうすぐ始まる新NISAについて、いくつかの留意点を紹介したいと思います。
2 つみたて投資枠で購入可能な金融商品は、成長投資枠でも購入可能であること
新NISAでは、年間投資枠の拡大とともに、従来のNISAでは、つみたてNISAは40万円、一般NISAは120万円という枠についてどちらかしか選択することができませんでした。
しかし、新NISAでは、つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円の合計最大年間360万円まで投資が可能になっており、併用が可能になりました。
つみたて投資枠の対象となる金融商品は、長期の積立、分散投資に適した一定の投資信託とされ、成長投資枠の対象となる金融商品は、上場株式・投資信託などとされ、個別株の購入も可能です。
このことから、つみたて投資枠と成長投資枠は、まったく別個の制度として理解され、それぞれの枠で、それぞれの典型的とされる商品への投資を検討しがちな印象がありますが、成長投資枠では、つみたて投資枠で購入可能な商品に投資することも可能です。
したがって、成長投資枠も含めて、安定的とされ、実際人気のあるインデックス投資をすることが可能です。
3 非課税保有期間の無期限化しさらに枠の再利用が可能となったこと
従来の制度では、一旦売却すると、その金額分について非課税の枠として利用することはできませんでしたが、新NISAでは、売却した金額の枠について、翌年以降、非課税で利用することが可能となり、大きなメリットとして注目されています。
口座開設期間の恒久化も併せて、特に成長投資枠で値上がりが期待できる個別株を購入することも魅力的ですが、売却後に非課税枠として復活するのは、翌年の1月とされていることから、売却のタイミングについて難しい判断を迫られることになりそうです。
4 終わりに
以上のとおり、新NISAは、十分な税優遇制度であり、賢く利用したいものですが、当然ながら元本割れのリスクもあります。
弁護士として、投資の失敗により苦しんだ方の依頼を受けた経験からすると、軽々しくお勧めすることはできない面もありますが、少しずつ、利用してみるのもよいかもしれません。
上告とは、一般に、未確定の控訴審の終局判決に対する法律審への上訴をいいます。
民事訴訟法上、上告は、上告の提起と上告受理の申立ての二つの方法が制度として規定されています。
上告の提起は、控訴審の終局判決に憲法違反または民事訴訟法に定める絶対的上告理由ががある場合にできます。
絶対的上告理由は、判決裁判所の構成違反、判決に関与することができない裁判官の関与、専属管轄規定違反、法定代理権・訴訟代理権の欠缺、口頭弁論公開違反、判決の理由不備又は理由の食違いが定められています。
上告受理の申立ては、控訴審の終局判決に法令違反があった場合に、上告裁判所が上告受理の申立てを受理した場合に限って、上告受理申立て理由が上告理由とみなされ、上告の効力が付与されることになります。
手数料は、訴え提起の手数料の2倍に設定されています。
先日、最高裁判事を退官した山口厚先生の新刊が成文堂が出版されるようです。
タイトルは、「犯罪論の基底と展開」で、最高裁判事の経験を踏まえた記載があるのか楽しみです。
令和5年7月13日から施行されている不同意性交等罪の構成要件である「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」の意味について、法務省が解説しています。
それによれば、同構成要件は、「同意しない意思を形成することが困難な状態」、「同意しない意思を表明することが困難な状態」、「同意しない意思を全うすることが困難な状態」という3つの状況が想定されていることが明確です。
「嫌だ」と言ったにもかかわらず性的行為をされてしまった事案においては、上記の「同意しない意思を形成することが困難な状態」、「同意しない意思を表明することが困難な状態」には該当せず、「同意しない意思を全うすることが困難な状態」に該当するかどうかを検討することになることも法務省の解説がなされています。