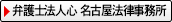改正債権法により,いわゆる約款について定められました(定型約款について民法548条の2から548条の4)。
改正債権法の原則的な施行時期は,十分な周知期間と準備期間を確保する観点から,2020(令和2)年4月1日とされましたが,定型約款については,施行日前に締結された契約にも,改正後の規定が適用されることが,改正法附則33条1項本文で規定されました。
このことは,従来,約款による契約の成立要件等についての確立した見解がない状況で,改正債権法により新たに合理的な規律を設けたものであることから,約款により成立した契約の当事者に施行日以後に限定して一定の規律に服すればよいという期待があるとはいえないことによるものと説明されています。
改正附則33条1項但し書及び同2項及び3項は,現行債権法の規定によって効力を生じた場合,解除権を行使することができる者を除いて施行日の前日までに書面で反対の意思表示をした場合について,例外を定めています。
不動産の登記名義人が亡くなった場合にどのような相続登記をするかについては,その相続の態様に応じてしかるべき登記手続をする必要があります。
遺言がある場合にはそれに従って登記手続をすることになりますが,遺言の内容が特定の相続人の遺留分を侵害するものであった場合には,遺留分減殺請求がされることもあります。
被相続人Aが遺言によって相続人Bに対して不動産,甲・乙・丙を相続させる,としていた場合に,他の相続人Cが遺留分減殺請求をして甲不動産の所有権を取得したケースではどのような登記申請をすべきかを考えてみましょう。
まずBについては甲乙丙について●年●月●日相続を原因とする所有権移転登記をB単独で申請することができます。
一方でCからの登記申請については二通りの登記申請が考えられます。
一つ目のケースは既にAからBへの所有権移転登記が完了していた場合です。
この場合には甲不動産について○年○月○日遺留分減殺を原因として所有権移転登記を申請することになりますが(昭和30年5月23日民甲973号),注意しなくてはならないのがこの場合にはCのみならず登記義務者としてBの協力が必要になる点です。
Bの協力なしにCが単独で登記申請をするためには裁判,調停等の手続を経る必要があります。
二つ目のケースはBの相続登記がいまだなされていない場合です。
この場合Cは甲不動産について●年●月●日相続を原因とする所有権移転登記をC単独で申請することができます。
実際には甲不動産の所有権はAからAの死亡日にBへ,Cからの遺留分減殺請求がBに到達した日にBからCへと移っているわけですが,登記簿上はAの死亡日付でAからCへ所有権が移転した,との公示がされることになります。
なお,令和元年7月1日からは,遺留分に関する権利行使(遺留分減殺請求権という呼称から,「遺留分侵害額の請求」とされました。)の効果は,物権的効果は生じず,金銭債権は発生することとされます(改正民法1046条1項)。
現在,司法書士法の改正が検討されているようです。
主な項目として,1人でも司法書士法人を設立可能となることのほか,司法書士の懲戒について7年間の除斥期間が定められることが検討されています。
自動車損害賠償保障法3条の「運行供用者」は、「運行支配」と「運行利益」の要素から判断する二元説が判例・通説とされています。
運行支配は危険責任、運行利益は報償責任に対応すると説明されます。
最高裁平成30年12月17日判決の事案は、生活保護を受けていたAはが、弟である被上告人に対して名義貸与を依頼し,被上告人が承諾、Aが本件自動車を購入し,所有者及び使用者の各名義を被上告人としたというものです。
最高裁は、「被上告人は,Aからの名義貸与の依頼を承諾して,本件自動車の名義上の所有者兼使用者となり,Aは,上記の承諾の下で所有していた本件自動車を運転して,本件事故を起こしたものである。Aは,当時,生活保護を受けており,自己の名義で本件自動車を所有すると生活保護を受けることができなくなるおそれがあると考え,本件自動車を購入する際に,弟である被上告人に名義貸与を依頼したというのであり,被上告人のAに対する名義貸与は,事実上困難であったAによる本件自動車の所有及び使用を可能にし,自動車の運転に伴う危険の発生に寄与するものといえる。また,被上告人がAの依頼を拒むことができなかったなどの事情もうかがわれない。そうすると,上記2(3)のとおり被上告人とAとが住居及び生計を別にしていたなどの事情があったとしても,被上告人は,Aによる本件自動車の運行を事実上支配,管理することができ,社会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう監視,監督すべき立場にあったというべきである。したがって,被上告人は,本件自動車の運行について,運行供用者に当たると解するのが相当である。」と判示し、運行供用者に該当する判断をしました。
商取引においては、商人が氏名や名称を黙秘する必要性がある場面が想定できることから、商法548条は、当事者が相手方に氏名や名称を示さないように仲立人に命じたときには、仲立人は従うべきことを規定しています。
この場合には、結約書や仲立人日記帳の謄本にも、氏名や名称を記載できないこととされます。
なお、仲立人による媒介により契約が成立してからも氏名黙秘義務を認めている点については、疑問も指摘されています。
また、商法549条は、仲立人が当事者の一方の氏名や名称を隠して媒介を行った場合には、仲立人は成立した契約を自ら履行する義務(介入義務)を負うことを規定しています。
匿名の当事者が契約上の債務を負担するのが本来ですが、仲立人が氏名や名称を開示しても、介入義務がなくなるものとは解されていないようです。
この介入義務については、仲立人の資力が乏しい場合が多いことを理由に実益のある規定とは思われない旨の指摘もされています。
〈商法〉
第五章 仲立営業
(定義)
第543条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。
(当事者のために給付を受けることの制限)
第544条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。
(見本保管義務)
第545条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。
(結約書の交付義務等)
第546条 当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。
二 当該行為の年月日及びその要領
2 前項の場合においては、当事者が直ちに履行をすべきときを除き、仲立人は、各当事者に結約書に署名させ、又は記名押印させた後、これをその相手方に交付しなければならない。
3 前2項の場合において、当事者の一方が結約書を受領せず、又はこれに署名若しくは記名押印をしないときは、仲立人は、遅滞なく、相手方に対してその旨の通知を発しなければならない。
(帳簿記載義務等)
第547条 仲立人は、その帳簿に前条第1項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
2 当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。
(当事者の氏名等を相手方に示さない場合)
第548条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第2項の謄本にその氏名又は名称を記載することができない。
第549条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。
(仲立人の報酬)
第550条 仲立人は、第546条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。
2 仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。
原審は,以下のとおり判示して損害賠償請求を一部認めていました。
「 (1) 本件仮差押申立ては,当初からその保全の必要性が存在しないため違法であり,被上告人に対する不法行為に当たる。(2) 本件仮差押命令の発令当時,被上告人と本件第三債務者との取引期間は1年4箇月であり,被上告人におけるその他の大手百貨店との取引状況等をも併せ考慮すると,被上告人は,本件仮差押申立てがされなければ,本件第三債務者との取引によって少なくとも3年分の利益を取得することができた。そして,本件仮差押命令の送達を受けた本件第三債務者が,被上告人の信用状況に疑問を抱くなどして被上告人との間で新たな取引を行わないとの判断をすることは,十分に考えられ,上告人はこのことについて予見可能であったから,本件仮差押申立てと本件逸失利益の損害との間には相当因果関係がある。」
最高裁は以下のとおり判示して破棄差戻の判断をしました。
「被上告人は,平成27年1月から平成28年4月までの1年4箇月間に7回にわ たり本件第三債務者との間で商品の売買取引を行ったものの,被上告人と本件第三債務者との間で商品の売買取引を継続的に行う旨の合意があったとはうかがわれないし,被上告人の主張によれば,上記の期間,本件第三債務者の被上告人に対する取引の打診は頻繁にされてはいたが,これらの打診のうち実際の取引に至ったものは7件にとどまり,四,五箇月にわたり取引が行われなかったこともあったというのであって,被上告人において両者間の商品の売買取引が将来にわたって反復継続して行われるものと期待できるだけの事情があったということはできない。
これらのことからすると,本件第三債務者が被上告人との間で新たな取引を行うか否かは,本件第三債務者の自由な意思に委ねられていたというべきであり,被上告人と本件第三債務者との間の取引期間等の原審が指摘する事情のみから直ちに,本件仮差押申立ての当時,被上告人がその後も本件第三債務者との間で従前と同様の取引を行って利益を取得することを具体的に期待できたとはいえない。
そして,金銭債権に対する仮差押命令及びその執行は,特段の事情がない限り,第三債務者が債務者との間で新たな取引を行うことを妨げるものではないし,本件仮差押命令の債務者である被上告人は,前記2(1)のとおりの売上高及び資産を有する会社であったところ,本件仮差押命令の執行は,本件仮差押命令が本件第三債務者に送達された日の5日後である平成28年4月28日には取り消され,その頃,本件第三債務者に対してその旨の通知がされており,本件第三債務者が被上告人に新たな商品の発注を行わない理由として本件仮差押命令の執行を特に挙げていたという事情もうかがわれない。
これらのことに照らせば,本件第三債務者において本件仮差押申立てにより被上告人の信用がある程度毀損されたと考えたとしても,このことをもって本件仮差押申立てによって本件逸失利益の損害が生じたものと断ずることはできない。 以上を総合すると,本件仮差押申立てと本件逸失利益の損害との間に相当因果関係があるということはできない。 」
弁護士としては,継続的な取引が期待できる契約関係ではないという事例での判断だと思いますが,仮差押えが違法と判断された理由と違法行為と損害の因果関係の有無の判断方法が参考になります。
従来、相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)がなされた場合、権利を承継した相続人が単独で登記申請することができたことから、最高裁平成11年12月16日は、遺言執行者の職務は顕在化せず、登記手続きをするべき権利も義務も有しないと判示しました。
しかし、改正民法899条の2第1項は、法定相続分を超える権利の承継については、対抗要件なく第三者に権利の取得を対抗することができないことを規定したことから、改正民法1014条2項は、遺言執行者が、特定財産承継遺言により財産を承継する受益相続人のために対抗要件を具備する権限を有することを明確化しました。
なお、改正民法のもとでも、受益相続人が単独で登記を申請することはできると解されています。
配偶者居住権は、①配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に居住しており、かつ、②⑴当該建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割がされた場合、⑵遺贈がされた場合、⑶死因贈与がされた場合に成立します(改正民法1028条)。
改正民法1029条は、家庭裁判所が、①共同相続人の間で配偶者に配偶者居住権を取得させることについて合意が成立している場合に加えて、②配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認める場合に限り、配偶者居住権を取得させる審判をすることができることを定めています。
配偶者居住権により、家族信託の活用場面として期待されている機能が代替できるとの評価もされていますが、附則10条2項は、施行日前にされた遺贈についてついては適用しないこととしています。
商法521条は、商人間における特別の留置権を規定しています。
①当事者双方が商人であること、②被担保債権が当事者双方のために商行為であること、③留置権の目的物が債務者の所有に属する物または有価証券であること、④債務者との間における商行為によって、債務者の占有に帰したものであること(被担保債権と個別的関連性があることは要求されない点で民事留置権と異なります。占有取得の原因が債務者との商行為、例えば、債権者・債務者間の寄託契約や賃貸借契約など)、⑤被担保債権の弁済期が到来していること、が要件として定められています(521条ただし書は、特約による留置権成立の排除を認めています)。
③との関連で、最高裁平成29年12月14日判決は、留置の目的物に不動産が含まれると判示しました(占有を要件とせず登記の前後により優先権が決定される抵当権との競合により不動産取引の安全を害するのではないかという観点から議論がありました。)。
また,民事留置権は,目的物が債務者の所有である必要がない点は,それぞれの留置権の沿革が異なることによるものと考えられ,合理性について疑問も生じるところです。
商事留置権の効力は商法に規定がないことから民法296条以下の規定によることとなり、留置権者は弁済を受けるまで留置目的物を留置し、これにより生ずる果実(民法88条)を取得することはできるが(民法297条)、留置目的物を売却してその代金を自己の債権に充当することはできず、また、競売にかけることはできるが(民事執行法195条)、換価代金について優先弁済を受けることはできないこととされています。
なお商法は、代理商(31条)、問屋(557条)、運送取扱人(562条)、運送人(574条)の留置権も定めています。
最高裁は、いわゆる相続させる旨の遺言(改正民法では、特定財産承継遺言)や、相続分の指定が遺言でされた場合に、登記等の対抗要件を具備しなくても、権利の取得を第三者に対抗することができるとしていました。
改正民法899条の2第1項は、「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分〔法定相続分〕を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。」と定め、相続を原因とする権利変動(遺産分割、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈)について利益を受ける相続人は、対抗要件を備えなければ法定相続分を超える権利の取得を第三者に主張することができないこととしました。
対抗要件を要求する範囲を法定相続分を超える部分に限定したのは、特定財産承継遺言や相続分の指定がなくても法定相続分に相当する権利については取得することができることから、相続による権利の承継について権利の競合が生じるのは、法定相続分を超える部分に限られることを理由とするものです。
なお、理論的な問題として、受益相続人以外の相続人は(第三者に遺産を処分した)無権利者であり、その無権利者からの譲受人も無権利者であることを前提としてきた判例理論あるいは従来の考え方の整合性なり位置づけは問題となり得ると考えられます。