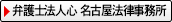改正民法では,債務引受に関する明文の規定が設けられました。
併存的債務引受の場合には,債務者と引受人は連帯債務者となるため両者の負担部分を観念することができ,別段の合意がなければ連帯債務における求償関係の規定(442条から445条)によることになります。
一方で,免責的債務引受の場合には,改正民法472条の3が,引受人が債務者に対して求償権を取得しない旨定めています。
債務者と引受人との間で別段の合意があれば別ですが,免責的債務引受の場合には,引受人が債務者が負っていた債務を引受人が引受け自己の債務として弁済することが理由とされます。
求償権を実質的に確保する手段としては,併存的債務引受契約によったり,債務者と引受人間で委任契約を締結して費用償還請求権を行使する方法や,保証契約を締結する方法などが考えられます。
働き方改革法等について,以下の本を購入して検討を進めています。
・「働き方改革とこれからの時代の労働法」(商事法務)
・「Q&A働き方改革法の解説と企業の実務対応」(ロギカ書房)
・「「働き方改革関連法」改正にともなう就業規則変更の実務」(清文社)
・「残業代請求の理論と実務」(旬報社)
不動産の相続登記について,改正がされました。
もともと不動産登記には対抗力が認められています(民法177条)。
一方で相続した不動産については,原則として法定相続分に限っては登記なくして第三者に対抗することができるとされていましたが,法定相続の場合,遺産分割による場合,遺言による場合,遺贈による場合など様々なケースについて,例外も存在しています。
些細な違いから結論が異なることは法的均衡を欠く,という観点から,今回の改正ではより明快に法定相続分を超える権利の取得については,登記なくして対抗することが出来ないものとされました(改正民法899条の2)。
今回の改正により,今後の相続についてより一層不動産登記の重要性が高まるものと考えられます。
相続法改正で配偶者居住権という制度が新設されました。
これまでの相続手続きでは,残された配偶者の生活をいかに保護するか,という問題がありました。
特に問題となるのは被相続人とその配偶者が被相続人名義の持ち家に住んでいたような場合で,他にこれといった相続財産が無いようなケースです。
このようなケースでは不動産を共同相続人で共有すればその後の管理が複雑になりますし,生存配偶者が単独で不動産を相続するとした場合には,他の相続人への遺留分その他の代償金などを支払う必要があるため,生存配偶者に十分な資力がなければ選べないことになります。
またほかの相続人が不動産を相続するとした場合には生存配偶者がその不動産を賃借して居住し続けるようなケースも考えられますが,そういった場合には賃料や契約解除の可能性といった面で,その後の生存配偶者の生活に支障をきたすおそれがあります。
そこで新設されたのが配偶者居住権(改正民法1028条以下)ということになります。
生存配偶者はその居住建物が相続財産の場合は,その全部を無償で,その終身までの間使用収益できる権利を取得します。
この場合には居住建物については生存配偶者以外の相続人が相続することとなります。
配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記が必要になります(改正民法1031条)。
刑事裁判は公開の法廷で行われますが,被害者の氏名等が起訴状朗読,冒頭陳述,書証の取調べ,論告・弁論等で明らかにされる場合には,特に,性犯罪をはじめとする被害者の名誉やプライバシーが著しく害されることが容易に想像されます。
そこで,刑事訴訟法290条の2は,被害者の特定事項を公判廷で明らかにしない旨の決定,いわゆる秘匿決定について定めています。
秘匿決定がなされた刑事事件では,弁護士,検察官はもちろん,裁判官も,名前をうっかり言わないよう細心の注意を払うことが求められます。
先日弁護人として出頭した名古屋高裁の秘匿決定事件では,秘匿決定がなされたことを示す筒が,弁護人,検察官,裁判官,及び,傍聴人にも一見して分かるように,複数立てられました。
標記の本は,労働事件の実務を担当するうえで,是非とも参照するべき文献の一つだと考えられています(今年愛知県弁護士会で実施されている労働法ゼミのテキストでもあります。)。
第16講「普通解雇と解雇権濫用法理」は,伊良原恵吾裁判官の担当です。
伊良原裁判官の問題意識は,普通解雇,特に「能力不足,成績不良等の人的理由による」普通解雇の有効性判断について,単なる杓子定規的な「準則」的運用ではない,一定の予見可能性と具体的妥当性をもたらす「もの差し」(判断基準)の探求を行うべきという点にあります。
上記「ものさし」とは,具体的には,①将来的予測の原則,及び,②最終的手段の原則,を指します。
内容として,それぞれ,①雇用契約の履行に支障を及ぼす債務不履行事由が将来にわたって継続するものと予測される場合に(根本論文「ドイツの議論状況も参考にすれば,継続的契約関係における契約の解消手段としての「解雇」は,「解除」と異なり,将来効を有する権利として,過去の債務不履行に対する単なる制裁として位置づけられるのではなく,その目的は契約関係が何らかの事情で破綻しているため,将来に向けて継続的契約関係を解消する点にある。したがって,解雇権のこうした本来的な性格に鑑みれば,解雇事由が現に客観的に存しているだけでなく,将来においてもその事由が継続することが解雇に際して求められることは必然的な要請であると考える。」),②その契約を解消するための最終手段として行使されるべきもの(根本論文「解雇権という,継続的契約関係の他方当事者の利益に必然的に影響を与える契約解消型形成権に伴って課される必然的な要請(他者の利益を侵害する故に目的と手段が均衡することが要請される)だと考える」)と主張しています。
労働者側の主張立証上の留意点として,使用者の雇用維持義務を大きく後退させるようなものではないことを明確にした上で使用者の労働能率・勤務成績に対する評価に対する反論に加え,指導・注意に従ったか,向上への意欲はあるか,労働能率・勤務成績不良もやむを得ないといえる合理的な特段の事情があるか,が挙げられています。
使用者側の主張立証上の留意点として,就業規則記載の解雇事由に着目した立証に加え,労働能率・勤務成績向上のための指導,注意等をしたか,人事管理に不適切なところはなかったか,採用時に特段の能力があることを条件としていたか,他に配置する部署が存在したか,本人の雇用を継続することによって会社業務の正常な遂行に与える影響は大きいか,という点があげられています。
伊良原裁判官の問題意識は,根本到教授の論文を参考としたものである旨明記されているところですが,実務でよく参照される類書にはない視点ということもできそうであり,一弁護士としては,慎重な検討が必要なのではないかという感想を持ちました。
伊良原裁判官は,17講「解雇事由が併存する場合における解雇権濫用法理の運用」も執筆されており,あわせて参照するべきだと考えられます。
特に,就業規則に規定された普通解雇事由についての例示列挙説と限定列挙説の対立の実務上の意味についての分析は参考になりました。
現行民法642条は,注文者が破産手続開始決定を受けた場合の請負人の有する解除権の行使について,文言上制限をしていないことから,完成後であっても行使できると考えられていました。
しかし,改正民法642条1項ただし書は仕事の完成後は,損害の拡大を防止するために契約の解除を認める必要はないこと等を考慮し,請負人は注文者の破産手続開始による解除をすることができない旨定めています。
現民法512条は相殺の充当について,単純に弁済の充当の規定を準用していますが(488条から491条),民法506条に定められているとおり相殺には遡及効がある点で弁済とは異なる考慮が必要と考えられていました。
そこで改正民法512条は,債権者が債務者に有している1個または数個の債権と債権者が債務者に負担している1個または数個の債務について,⑴充当の順序に関する合意をしたときはそれによって消滅すること,⑵合意をしないときは,債権者の債権と負担する債務は相殺適状となった時期の順序に従って相殺によって消滅すること(同条1項),相殺適状の時期が同じ元本債権相互間と利息・費用債権の充当について,相当する弁済の充当の規定を準用しています(同条2項)。
就業規則の解雇条項は解雇事由を限定列挙したものか、例示にすぎないかについては学説上の争いがあるようです。
労働基準法89条3号により解雇事由の定めが就業規則の絶対的必要的記載事項とされたことが、限定列挙説の根拠と主張されることもありますが、実務上は、解雇事由として包括的な条項が規定されていることが多く、実際上の違いはないと一般に考えられています。
労働基準法が改正され,平成31年4月から,年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して,年次有給休暇の日数のうち年5日については,使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
使用者は,時季指定にあたっては,労働者の意見を聴取し,その意見を尊重するよう努めなければならず,労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し,3年間保存することも求められます。
なお,年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者や計画的付与により5日以上付与された労働者に対しては,使用者による時季指定は不要であり,労働者が自ら申し出て取得した年次有給休暇の日数,計画的付与により与えられた日数については,5日から控除することができることになります。
これまでの有給休暇の取得状況などをふまえ,具体的な対策が求められることになります。