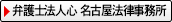いわゆる名古屋自動車学校事件の最高裁判決について
1 名古屋自動車学校事件とは
定年退職後に、有期労働契約を締結して勤務していた労働者が、無期労働契約を締結している労働者との間における基本給、賞与等の相違は労働契約法(平成30年法律第71号による改正前)20条に違反するもの主張して、不法行為等を根拠に、差額の損害賠償等を求めたものです。
一審名古屋地裁判決の内容は、実務の指針とまではいえないものの、同種の裁判例がない状況において、特に使用者側の弁護士に参照されることの多いものでした。
2 事実関係等(最高裁判決の認定から)
⑴ 無期労働契約を締結して自動車教習所の教習指導員の業務に従事していた者(以下「正職員」という。)の賃金は、月給制であり、基本給、役付手当等で構成されていた。このうち、基本給は一律給と功績給から成り、役付手当は主任以上の役職に就いている場合に支給するものとされていた。
正職員に対しては、夏季及び年末の年2回、賞与を支給するものとされ、その額は、基本給に所定の掛け率を乗じて得た額に10段階の勤務評定分を加えた額とされていた。
正職員は、役職に就き、昇進することが想定されており、その定年は60歳であ った。
⑵ 平成25年以降の5年間における基本給の平均額は、管理職以外の正職員の うち所定の資格の取得から1年以上勤務した者については、月額14万円前後で推移していた。
上記平均額は、上記の者のうち勤続年数が1年以上5年未満のもの (以下「勤続短期正職員」という。)については月額約11万2000円から約12万5000円までの間で推移していたが、勤続年数に応じて増加する傾向にあり、勤続年数が30年以上のものについては月額約16万7000円から約18万円までの間で推移していた。
平成27年の年末から令和元年の夏季までの間における賞与の平均額は、 勤続短期正職員については、1回当たり約17万4000円から約19万6000 円までの間で推移していた。
⑷ いわゆる高年法9条1項2号所定の継続雇用制度を導入しており、定年退職する正職員のうち希望する者については、期間を1年間とする有期労働契約を締結し、これを更新して、原則として65歳まで再雇用することとしていた。
⑸ 正職員に適用される就業規則等とは別に、定めていた嘱託規程においては、嘱託職員の賃金体系は勤務形態によりその都度決め、賃金額は経歴、年齢その他の実態を考慮して決める旨や、再雇用後は役職に就かない旨等が定められていた。
有期労働契約においては、勤務成績等を考慮して「臨時に支払う給与」(以下「嘱託職員一時金」という。)を支給することがある旨が定められていた。
⑹ア 被上告人X1 は、昭和51年頃以降正職員として勤務し、主任の役職にあった平成25年7月12日、退職金の支給を受けて定年退職し、定年退職後再雇用され、同月13日から同30年7月9日までの間、嘱託職員として教習指導員の業務に従事した。基本給は、定年退職時には月額18万1640円、再雇用後の1年間は月額8万1738円、その後は月額7万4677円であ った。
定年退職前の3年間において、1回当たり平均約23万300 0円の賞与の支給を受けていたところ、再雇用後、有期労働契約に基づき、正職員に対する賞与の支給と同時期に嘱託職員一時金の支給を受けており、その額は、平成27年の年末以降、1回当たり8万1427円から10万5877円まででだった。
イ 被上告人X2は、昭和55年以降正職員として勤務し、主任の役職にあった平成26年10月6日、退職金の支給を受けて定年退職し、定年退職後再雇用され、同月7日から令和元年9月30日までの間、嘱託職員として教習指導員の業務に従事した。基本給は、定年退職時には月額16万7250円、再雇用後の1年間は月額8万1700円、その後は月額7万2700円であった。
定年退職前の3年間において、1回当たり平均約22万50 00円の賞与の支給を受けていたところ、再雇用後、嘱託職員一時金の支給を受けており、その額は、平成27年の年末以降、1回当たり7万3164 円から10万7500円までであった。
ウ 被上告人らは、再雇用後、厚生年金保険法及び雇用保険法に基づき、老齢厚生年金及び高年齢雇用継続基本給付金を受給した。
被上告人X1は、平成27年2月24日、上告人に対し、自身の嘱託職員と しての賃金を含む労働条件の見直しを求める書面を送付し、同年7月18日までの 間、この点に関し、上告人との間で書面によるやり取りを行った。また、被上告人X1は、所属する労働組合の分会長として、平成28年5月9 日、上告人に対し、嘱託職員と正職員との賃金の相違について回答を求める書面を 送付した。
3 原審名古屋高裁の判断(被上告人らの 基本給及び賞与に係る損害賠償請求を一部認容すべき。)
被上告人らについては、定年退職の前後を通じて、主任の役職を退任したことを 除き、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲に相違がなかったにもかかわらず、嘱託職員である被上告人らの基本給及び嘱託職員一時金の額は、定年退職時の正職員としての基本給及び賞与の額を大 きく下回り、正職員の基本給に勤続年数に応じて増加する年功的性格があることから金額が抑制される傾向にある勤続短期正職員の基本給及び賞与の額をも下回っている。
このような帰結は、労使自治が反映された結果でなく、労働者の生活保障の観点からも看過し難いことなどに鑑みると、正職員と嘱託職員である被上告人らとの間における労働条件の相違のうち、被上告人らの基本給が被上告人らの定年退職時の基本給の額の60%を下回る部分、及び被上告人らの嘱託職員一時金が被上告人らの定年退職時の基本給の60%に所定の掛け率を乗じて得た額を下回る部分は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる。
4 最高裁の判示
労働契約法20条は、有期労働契約を締結している労働者と無期労働契約を締結している労働者の労働条件の格差が問題となっていたこと等を踏まえ、有期労働契約を締結している労働者の公正な処遇を図るため、その労働条件につき、期間の定めがあることにより不合理なものとすることを禁止したものであり、両者の間の労働条件の相違が基本給や賞与の支給に係るものであったとしても、それが同条にいう不合理と認められるものに当たる場合はあり得るものと考えられる。
もっとも、その判断に当たっては、他の労働条件の相違と同様に、当該使用者における基本給及び賞与の性質やこれらを支給することとされた目的を踏まえて同条所定の諸 事情を考慮することにより、当該労働条件の相違が不合理と評価することができる ものであるか否かを検討すべきものである(最高裁令和元年(受)第1190号、 第1191号同2年10月13日第三小法廷判決・民集74巻7号1901頁参照)。
⑴ 基本給
ア 管理職以外の正職員のうち所定の資格の取得から1年以上勤務した者の基本給の額について、勤続年数による差異が大きいとまではいえないことからすると、正職員の基本給は、勤続年数に応じて額が定められる勤続給としての性質のみを有するということはできず、職務の内容に応じて額が定められる職務給としての性質をも有するものとみる余地がある。他方で、正職員については、長期雇用を前提として、役職に就き、昇進することが想定されていたところ、一部の正職員には役付手当が別途支給されていたものの、その支給額は明らかでないこと、正職員の基本給には功績給も含まれていることなどに照らすと、その基本給は、職務遂行能力に応じて額が定められる職能給としての性質を有するものとみる余地もある。
正職員に対して、上記のように様々な性質を有する可能性がある基本給を支給することとされた目的を確定することもできない。
嘱託職員は定年退職後再雇用された者であって、役職に就くことが想定されていないことに加え、その基本給が正職員の基本給とは異なる基準の下で支給され、被上告人らの嘱託職員としての基本給が勤続年数に応じて増額されることもなかったこと等からすると、嘱託職員の基本給は、正職員の基本給とは異なる性質や支給の目的を有するものとみるべきである。
しかるに、原審は、正職員の基本給につき、一部の者の勤続年数に応じた金額の推移から年功的性格を有するものであったとするにとどまり、他の性質の有無及び内容並びに支給の目的を検討せず、また、嘱託職員の基本給についても、その性質及び支給の目的を何ら検討していない。
イ 労使交渉に関する事情を労働契約法20条にいう「その他の事情」として考慮するに当たっては、労働条件に係る合意の有無や内容といった労使交渉の結果のみならず、その具体的な経緯をも勘案すべきものと解される。
上告人は、被上告人X1及びその所属する労働組合との間で、嘱託職員としての賃金を含む労働条件の見直しについて労使交渉を行ってい たところ、原審は、上記労使交渉につき、その結果に着目するにとどまり、上記見直しの要求等に対する上告人の回答やこれに対する上記労働組合等の反応の有無及び内容といった具体的な経緯を勘案していない。
ウ 以上によれば、正職員と嘱託職員である被上告人らとの間で基本給の金額が 異なるという労働条件の相違について、各基本給の性質やこれを支給することとされた目的を十分に踏まえることなく、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、その一部が労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法がある。
⑵ 嘱託一時金
被上告人らに支給された嘱託職員一時金は、正職員の賞与と異なる基準によってではあるが、同時期に支給されていたものであり、正職員の賞与に代替するものと位置付けられていたということができるところ、原審は、賞与及び嘱託職員一時金の性質及び支給の目的を何ら検討していない。上告人は、被上告人X1の所属する労働組合等との間で、嘱託職員としての労働条件の見直しについて労使交渉を行っていたが、原審は、その結果に着目するにとどまり、その具体的な経緯を勘案していない。このように、上記相違について、賞与及び嘱託職員一時金の性質やこれらを支給することとされた目的を踏まえることなく、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、その一部が労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法がある。
5 差戻審
最高裁の判示によれば、基本給の性質を詳細に検討することとなりますが、会社が果たして、基本給の性質や目的を特定して支給していたのか、ある意味では事後的に客観的な事情からその目的を特定する作業も必要となりそうです。
- 次の記事へ:ポケット六法令和6年版
- 前の記事へ:仮執行宣言付きの敗訴判決の言い渡しを受けた場合の対応