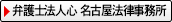権利が係争中の場合の所得の帰属時期に関する権利確定主義の考え方
1 所得税法36条1項が、「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする。」としている趣旨は、現実の収入がなくてもその収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとしてその権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという権利確定主義を採用したものと考えられます。
これは、理由付けの表現はいろいろあると思いますが、裁判例等では、所得税は経済的な利得を対象とするものであるから究極的には実現された収入によってもたらされる所得について課税するのが基本原則であるが、課税に当たって常に現実収入の時まで課税できないとすると納税者の恣意を許し課税の公平を期し難いこと、徴税政策上の技術的見地から課税庁が認定することが可能という意味で、権利の確定した時期をとらえて課税するのが妥当という説明がなされています。
裁判官や弁護士にとっても、権利が法的に確定したという基準は、分かりやすい基準と思えますが、具体的な事案においては非常に難しい判断が要求されることは、一連の裁判例が物語っています。
2 具体的にいかなる時期に収入の原因となる権利が確定したと考えるかについては、収入の原因となる権利ごとにその特質を考慮して決定せざるを得ないとも最高裁判例や裁判例は述べているところです。
ここで、収入の原因となる権利が争われている場合には、収入の実現の蓋然性も明らかではなく、権利が確定したとはいえないことから、裁判等で権利の争いが終結した時に権利が確定すると考えるべきという有力な学説があります。
権利「確定」主義なのですから、権利が確定していない限り、すなわち係争が終結しない限り、収入は帰属しないというのは、非常に単純明白で分かりやすいとも言えます。
なお、いくら係争中といっても、収入の帰属時期を恣意的に操作することを許さない観点から、当該権利の係争が、収入の時期を恣意的に操作するためのものではないことについても検討する必要があります。
なれ合い訴訟という用語もあり、その可能性を一応検討するべきということです。
3 納税者の立場からは、権利が係争中の場合には、最高裁判例上確立していると考えられる、管理支配主義からの検討を要する事案もあります。
管理支配主義は、その収入を受け取る権利が法的に確定していないにもかかわらず、それを「収入すべき金額」と扱う意味で、租税法律関係を不安定にするものであるから、その適用範囲は限定的・例外的であるべきというのが一般的な感覚だと思います。
管理支配主義を採用したとされる仙台賃料増額請求事件(最高裁昭和53年2月24日判決)では、訴訟が終結していない段階で、増額を求めた大家側の賃料に相当する金額が借主側から支払われた事案であり、納税者側の意思・欲求(請求)に基づく権利が、厳密には法的に確定していない段階で実現したものという整理が可能そうです。
いわゆる違法所得に関する利息制限法違反の利息が支払われた事件(最高裁昭和46年11月9日判決)においても、違法であるため当然保持する権限・権利は法的に確定はしませんが、まさしく納税者である貸主側の意思・欲求(請求)に基づいて納税者側に金銭が交付されたという整理が可能です。
現実に収受された約定の利息等の全部が制限超過利息の分まで課税の対象となる一方、未収である限りは、約定の履行時期が到来しても、「収入すべき金額」にはならないと判断したものです。
- 次の記事へ:令和5年9月に改正された精神障害の労災認定基準の概要
- 前の記事へ:名古屋地方裁判所の支部の駐車場